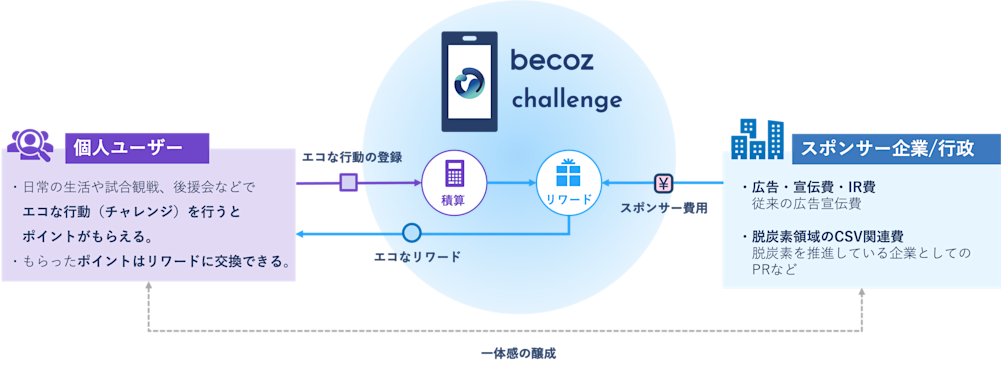株式会社DATAFLUCTは、使用済みプラスチックの再資源化と技術開発に取り組む株式会社アールプラスジャパンと協力し、東京都国立市で実施された業界横断型のプラスチック資源自主回収テストに参画しました。この度、アールプラスジャパンより、本取り組みの詳細な結果レポートが公開されましたのでお知らせします。
国立市での包括連携協定に基づく画期的な取り組み
この回収テストは、2024年2月1日にアールプラスジャパンが国立市および国立市社会福祉協議会と締結した包括連携協定に基づき実施されました。持続可能な循環型社会の実現、環境保全、環境教育の推進、地域コミュニティの活性化、そして地域福祉の向上を目的とした多角的な取り組みです。本プロジェクトには、アールプラスジャパンに資本参加する株式会社ヤクルト本社、三友プラントサービス株式会社、株式会社Mizkan、リスパック株式会社の4社に加え、協力企業としてSGムービング��株式会社、CBC株式会社、PSジャパン株式会社、そして株式会社DATAFLUCTが参画。業界の垣根を越えた連携が、プラスチック資源循環の新たなモデル構築を目指しています。
回収テストの成果と見えてきた可能性
回収対象となったのは、Mizkan、リスパック、ヤクルト本社が製造・販売する食品容器、具体的には納豆容器、弁当容器のフタ、乳酸菌飲料容器でした。テストは主に1日限りの回収イベントを3回実施し、回収量は回を追うごとに着実に増加。初回は約4kg、2回目は約9kg、3回目は約12kgと、市民の協力意欲の高まりが示されました。特筆すべきは、異物混入率が1%未満という低い水準で推移し、さらに低下傾向が見られたことです。これは、市民の高い分別意識を裏付ける結果と言えるでしょう。また、3回目の回収テストでは、イベント後1か月間の継続回収も試みられ、約15kgを回収しました。しかし、1日限りのイベントと比較して異物混入率が高まる傾向が見られ、長期的な回収における異物混入対策の重要性が浮き彫りになりました。特に、弁当のフタからは複数種類のプラスチック素材(PS、PP、PET)が混合して回収されており、アールプラスジャパンが開発を進める混合プラスチックのリサイクル新技術の重要性が改めて示されました。
市民アンケートから見えた課題とヒント
回収テストと並行して実施された市民アンケート調査では、プラスチックごみ問題への関心の高さや、普段から高い分別意識を持って行動していることが確認されました。一方で、容器回収における課題として、回収場所までの距離、家庭での保管スペースの確保、家族によるごみとの誤認、そして洗浄・乾燥の手間などが挙げられました。回収への協力意欲を高めるためには、回収したプラスチックがどのようにリサイクルされたかという結果の報告や、ポイント還元などのインセンティブ付与が有効であることが示唆されました。また、リサイクル容器への変更に伴う値上げを受容するとの回答が約26%あったことも、今後のビジネスモデルを考える上で重要な示唆を与えています。
今後の課題と展望
今回の実証実験を通じて、今後のプラスチック資源循環をより継続可能で拡大していくための課題も明らかになりました。長期的な回収テストにおいては、回収する側は異物混入対策の強化が必須であり、消費者側には回収の利便性向上とインセンティブの付与が不可欠です。持続可能な取り組みとするためには、最終製品への価格転嫁も視野に入れ、経済合理性を確保することが重要です。アールプラスジャパンは、今回の結果レポートを踏まえ、引き続きパートナー企業や自治体との連携を強化し、実用的なプラスチック資源循環モデルの確立を目指します。詳細なレポートは、アールプラスジャパンのウェブサイトで公開されています。ぜひご覧ください。