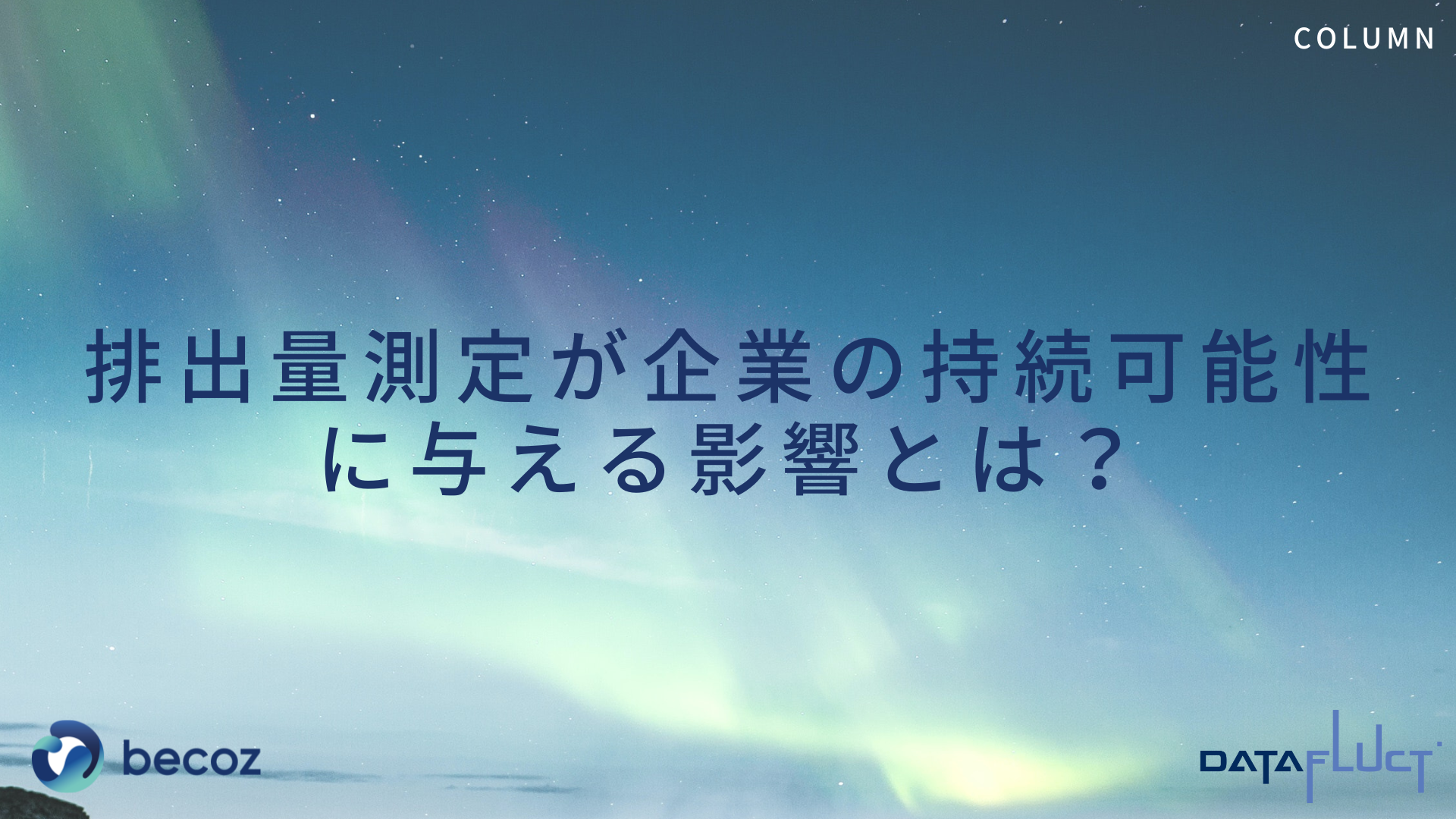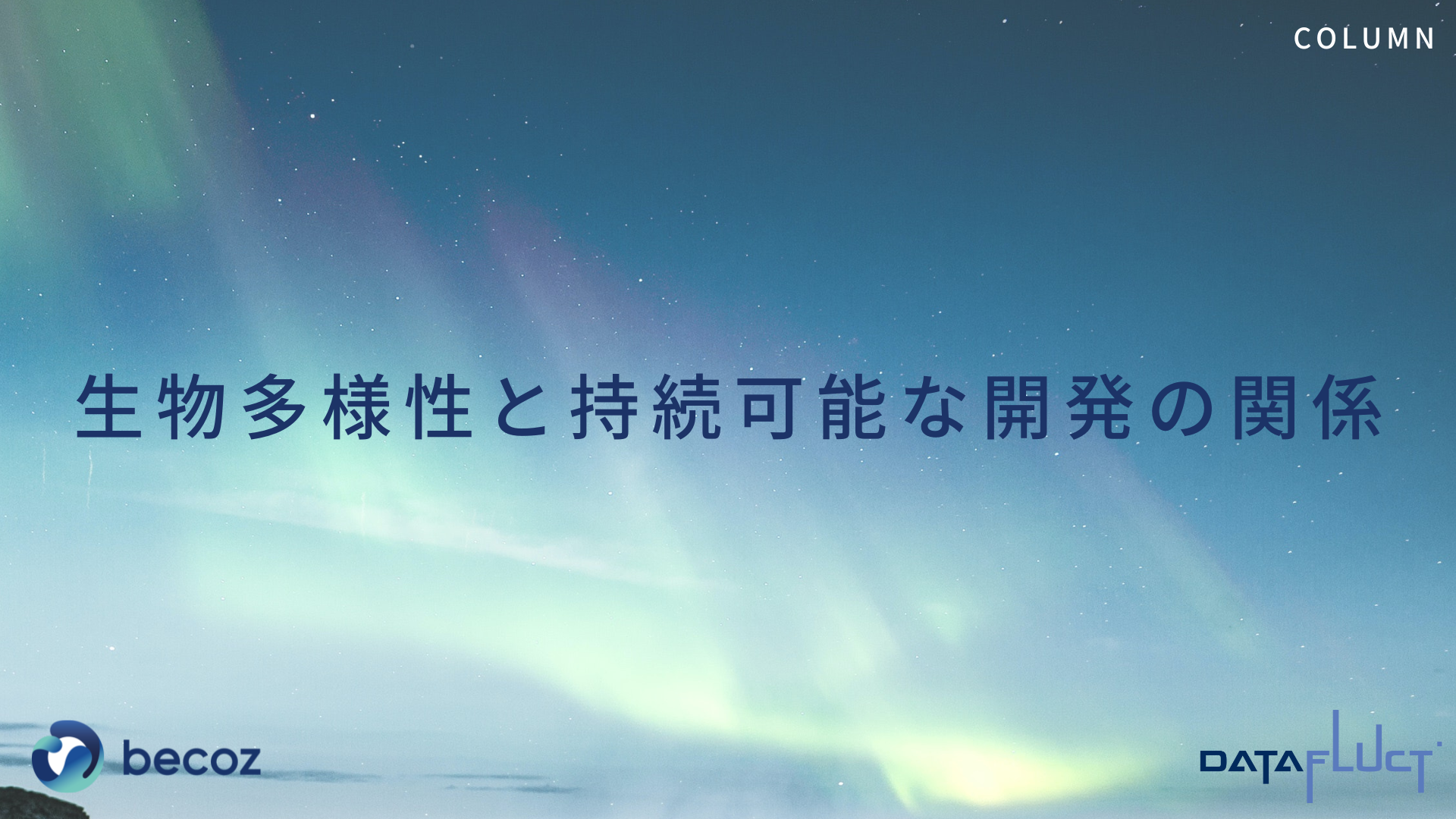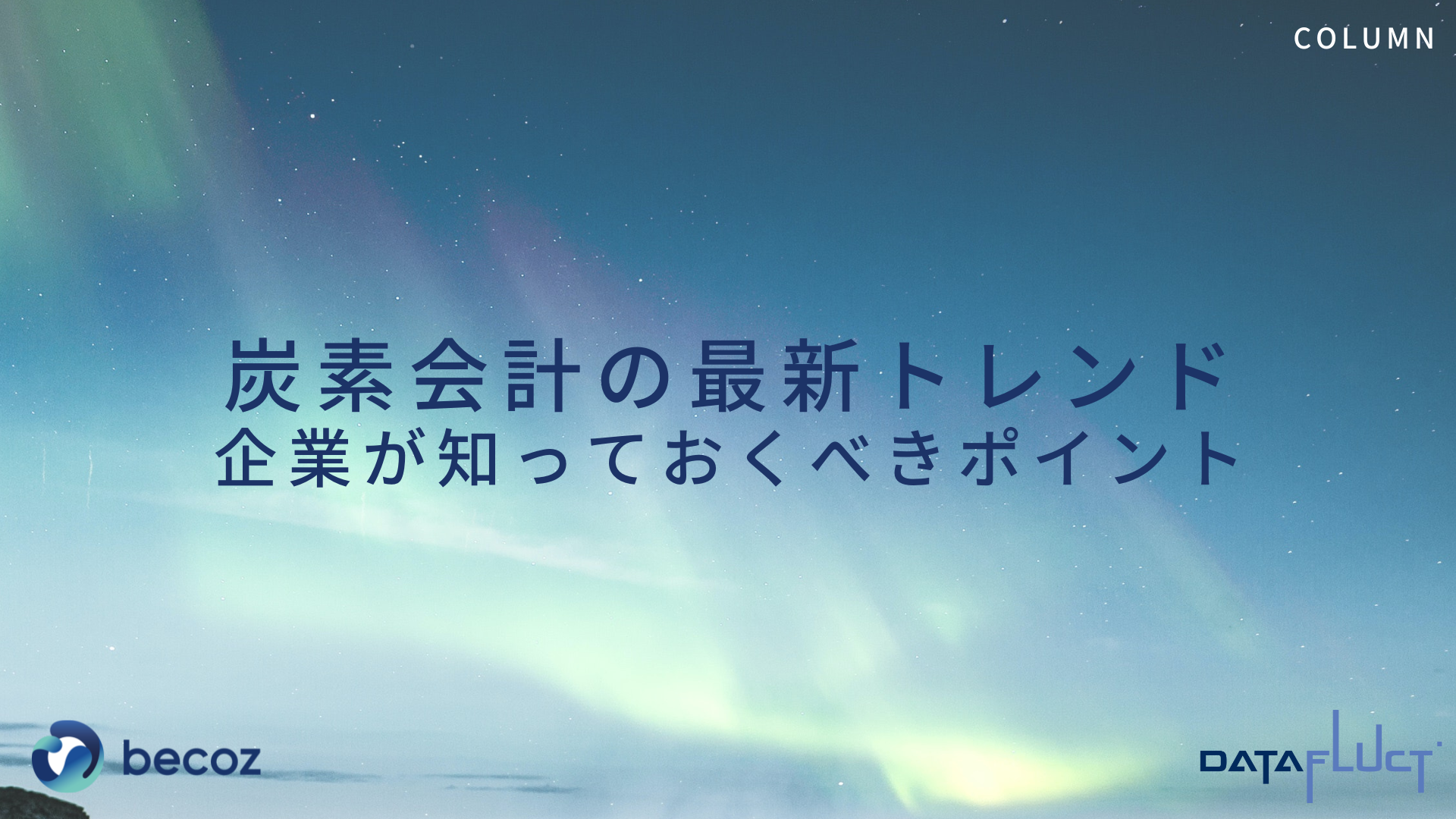「カーボンニュートラル」や「脱炭素」は地球温暖化について語られる上で必ずと言っていいほど出てくるキーワード。これらが重要だとは分かっていても、日本がどのような対応をしているのかまで詳しく知っている人は少数派だ。
また、環境のために少しでも行動をしたほうがいいと考えていたとしても、すぐに行動に移すのは大変なもの。そん��なときに知ってほしいのが、環境省が薦める行動指針である「カーボンニュートラルアクション30」(※1)。
一体どういうものなのだろうか。
世界と日本が向き合う「カーボンニュートラル」の今
温室効果ガス排出量を実質ゼロにする「カーボンニュートラル」
そもそもカーボンニュートラルとは、「人間が活動を行うことによって発生した温室効果ガスの排出量と吸収量をプラスマイナスゼロにすること」を意味する。
二酸化炭素などの温室効果ガスの多くは、石油や石炭、天然ガスなどといった化石燃料を燃やしたときに発生。これらは発電とも密接に関わっており、私たちの生活に必要不可欠な存在だ。
言い換えると、温室効果ガス排出量を減らすことはできても、完全にゼロにすることは非常に難しい。
そこで、植物を植え、森を増やし、減らしきれない温室効果ガスを吸収してもらい、トータルでの温室効果ガスの排出量と吸収量を同程度にし、“排出量を実質ゼロにしよう”とするのが「カーボンニュートラル」の考え方だ。
120以上の国と地域が「2050年のカーボンニュートラル」を目指す
2022年現在、カーボンニュートラルは世界共通の長期目標として掲げられている。その大元になっているのが、2015年12月にCOP21(国連気候変動枠組条約第21回締約国会議)で採択された「パリ協定」。これは世界全体で地球温暖化対策を進めていく枠組みだ。
パリ協定では、産業革命以�前と比べて、世界的な平均気温が2℃以上上昇しないようにすることを目指す「2℃目標」が掲げられ、さらに上昇幅を1.5℃に抑える努力を追求することが定められている。
世界の現状はどのようになっているのだろうか? 産業革命以前と比べると、すでに世界の平均気温は人間活動の影響で約1℃上昇している。今のままの暮らし方を続けていれば、2030年には1.5℃、2050年には4℃の上昇が予想されている。地球の平均気温が「4℃上昇」することは、惑星として生物が生育する環境自体が、現在と全く変わってしまうことを意味している。
この上昇幅を1.5℃以内に抑えるためには、2050年には脱炭素化を実現する必要があり、このデータにもとづいて、日本を含めた120以上の国と地域が「2050年にカーボンニュートラルを実現する」という目標を掲げているのだ。
日本では2030年までに46%削減が目標
次に日本の動きを見てみよう。パリ協定に呼応する形で、日本は2020年10月に「2050年までにカーボンニュートラル実現する」と宣言。それに伴い、2013〜2030年度の間で、温室効果ガスの46%削減を目指している。

そして2019年度、日本は二酸化炭素換算で12億1200万トンの温室効果ガスを排出。2018年には、二酸化炭素排出量が中国、アメリカ、インド、ロシアに次いで5位になっている。 まだまだ大量の二酸化炭素を排出しているが、実は6年連続で排出量は減少中。2019年度には、日本の温室効果ガス排出量は過去最少になっているのだ。
ただし、このペースで排出量を減らしていっても、2050年までにカーボンニュートラルを実現できないとされている。
こうしたデータを受けて日本�は現在までに、温室効果ガスの排出量に対する報告義務や排出量抑制などについて規定を定めた「改正地球温暖化対策推進法」を成立させるなど、カーボンニュートラルの実現に積極的に取り組んでいる。
カーボンニュートラルのために個人ができることは?
「ゼロカーボンアクション30」とは?
2021年6月、「国・地方脱炭素実現会議」において「地域脱炭素ロードマップ」が取りまとめられた。これは地域における「暮らし」「社会」分野を中心に、脱炭素社会の実現に向けた流れと具体例をまとめた資料だ。 その中に載っているのが、環境省が提唱するアクションリスト「ゼロカーボンアクション30」。
衣食住や移動、買い物などの日常生活に関する脱炭素のための具体的な行動と暮らしにおけるメリットが、8分類・30種類の行動としてまとめられ、一人ひとりが手軽にできる行動のヒントが紹介されているのだ。
●アクションリストの8分類
1. 電気などのエネルギーの節約や転換
2. 住居関係(建築素材、断熱や工法)
3. 移動関係(公共交通の利用、EV、動力のチョイス)
4. 食関係(フードマイレージ、フードロスへの働きかけなど)
5. 衣類、ファッション関係(素材や企業の取り組みでのチョイス)
6. ごみを減らす(再利用、パッケージの見直し)
7. 買い物・投資
8. 環境活動
自宅やオフィスで取り組めることは?
上記の8分類をもとに「ゼロカーボンアクション30」の中から、自宅やオフィスですぐに取り組めるアクションを一部紹介しよう。
●再生可能エネルギーへの切り替え
日本では電力小売自由化によって、個人・法人にかかわらず、電力会社を自由にえらべるようになった。なかには、再生可能エネルギー専用プランを提供している会社もある。電気料金の節約も兼ねて、一度契約を見直してみよう。
●クールビズ・ウォームビズ
暑い夏、寒い冬の気候に合わせた服装を選ぶことは、適切な冷暖房管理にもつながる可能性がある。自分の健康や快適さのためにもクールビズとウォームビズを取り入れてみよう。
●宅配サービスをできるだけ一回で受け取る
再配達を繰り返すことでトラックの稼働時間が増え、CO2排出量の増加につながってしまう。自宅で過ごす時を受取時間に指定するなど、お互いにとってスムーズな受け取り方ができるように努めてみよう。
●スマートムーブ
徒歩や自転車、公共交通機関を積極的に利用してみよう。運動量を増やすだけではなく、人混みの回避につながる可能性もある。また、自動車に乗る際は急発進や停車をさけるエコドライブを意識したり、カーシェアリングを利用したりすることもおすすめだ。
●食事を食べ残さない
外食やテイクアウトをする際には、自分が食べ切れる適度な量を買える店を選んでみよう。またどうしても食べきれなかった分は、持ち帰りサービス「mottECO」などを活用してみよう。
●長く着られる服をじっくり選ぶ
毎日必ず着る衣服��。だからこそ、長く使えて愛着がわく、こだわりの一着をしっかりと考えながら買ってみようお気に入りの服を着ることは、体型維持や健康管理のモチベーションにもつながる。
●マイバッグ、マイボトル、マイ箸、マイストロー等を使う
レジ袋有料化によって、使用する人が増えたエコバッグ。さまざまなデザインがあるので、自分の気に入ったものを探してみよう。 暑い時期にはマイボトルの活用もおすすめ。マイ箸やストローなども、徐々に取り入れてみよう。
ここで紹介したのは「ゼロカーボンアクション30」の一部。紹介した中には今日からアクションできそうなこともあったはずだ。挫折せずにじっくりと続けるためにも、まずは無理なくできるところから、少しずつ取り組んでみよう。
一人のアクションには、どんな意味があるの?
ここまで記事を読んでくださった人の中には、環境問題へ強い関心を寄せ、すでにさまざまな行動を起こしてしている人も多いはず。
しかし、具体的な変化がすぐには見えにくい気候変動という壮大なテーマについて真剣に考えるほど、「自分ができることは限られている」「頑張っているけど、一人でやっても変わらないじゃないか」と思ってしまうこともあるかもしれない。
そういった曇った気分を晴れやかにするために、私たち一人ひとりが環境問題に対してアクションを起こすことにはどんな意味があるのかを考えてみよう。
「気候変動問題」対策への負担感が強い日本
そもそ�も日本は、他国に比べて「気候変動問題に取り組むためには自分の暮らしのレベルを大きく下げる必要がある」など、「強い負担感」を感じている人が多いというデータがあるそうだ(2015年・世界市民会議で実施された調査結果より)。
つまり、「環境へ配慮した行動をとったほうがいい」と思いつつも、そのためには「今までの生活を大きく変えないといけない」と考えている人が多いのだ。
しかし、これまで紹介してきたように、今すぐ取り入れられることでも環境へ配慮することは可能。暮らしのクォリティーを落とさないばかりか、お金の節約や暮らしの快適さ向上につながる行動はたくさんある。
私たち一人ひとりがちょっとしたゼロカーボンアクションを取り入れることで、そういった行動の認知度を上げていくことも意識してみるといいかもしれない。それも回り回って環境負荷を軽減するために効果があるのだから。
カーボンニュートラルへ自然に近づける社会づくりが重要
また、「自分は十分に環境へ配慮した行動をしているから大丈夫」と考えている方もいるかもしれない。しかし、残念ながら、ほんの一部の人だけが行動しても、社会全体として気候変動問題を解決することはできないという「フリーライダー問題」が存在する。
世の中には多様な価値観があり、興味関心が異なる人々がたくさんいる。そのため、規制や罰則などが定められない限り、全員が気候変動問題について非常に高い関心を持ち、ライフスタイルを変えるように強制することはできない。
こうした状況を踏まえると、社��会全体で気候変動問題を根本的に解決するためには「誰もがいつのまにか環境配慮をした行動が取れる社会へシステムを変革させること」が必要なのではないだろうか。
例えば、「お店に並んでいる商品が当たり前のように環境配慮されている」「環境配慮商品を購入・製造すると税金負担が軽減される」など、企業や個人が合理的あるいは無意識に、環境に配慮した選択肢を取れるような仕組みが整えば、カーボンニュートラルの目標達成へ確実に前進していくだろう。2022年5月時点で、既設照明のLED普及率が50%を超えたことも、無意識に誰でも取り組める省エネの選択=クールチョイスの一例だろう。
そういった社会の実現のために、私たち一人ひとりの生活者・消費者が環境問題を重視していることを、国や企業に伝え、環境配慮が前提の社会づくりを求めていくことが非常に大切になる。
「フリーライダー問題」は、裏を返せば、誰のどんな小さな行動でも、人類全体の共通目標である、カーボンニュートラルへの貢献につながっていることを意味する。そんな思いを胸に、小さなアクションを積み重ねることを提案したい。
脚注
(※1)環境省の「ゼロカーボンアクション30」については、環境省のクールチョイスHPをご覧ください。(https://ondankataisaku.env.go.jp/coolchoice/)
(text by becoz / illustration by Natsumi Kachi)